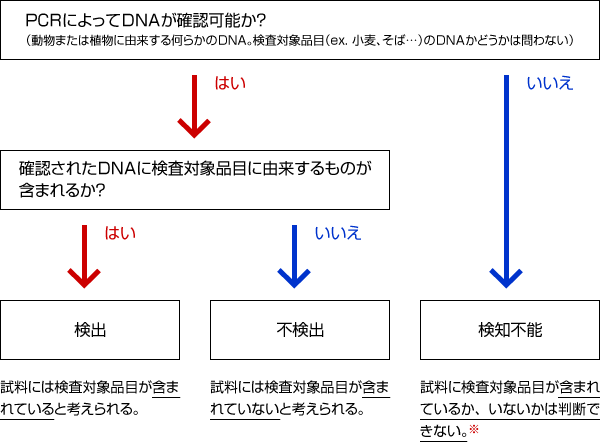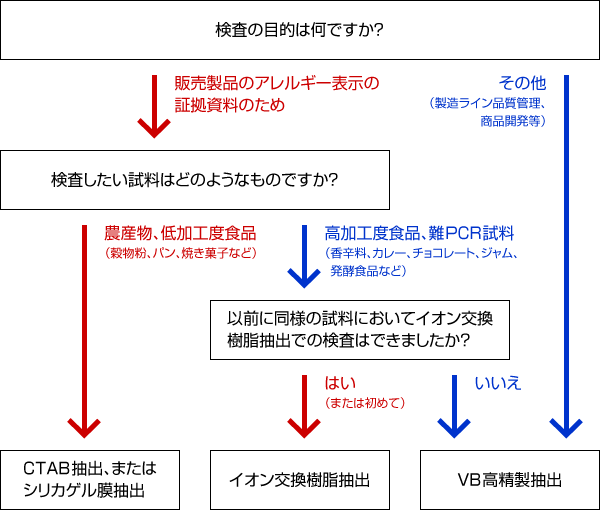食物アレルギー(アレルゲン)検査
よくある質問
ご依頼の前に、検査業務規約をご確認ください。
- どの検査方法を選んだらよいですか?
消費者庁次長通知「食品表示基準について」平成27年03月30日 消食表第139号 別添「アレルゲンを含む食品の検査方法」では、表示義務品目において、まずはスクリーニング検査(定量検査)としてELISA法を用いた検査を実施します。もし陽性反応が出た場合は、ウエスタンブロット法やPCR法を用いた確認検査(定性検査)を追加で実施する流れとなっています。
一般的には、表示義務の有無に関わらず、上記の考え方に準じて検査方法を選択することが多いようです。しかし、表示推奨品目にはELISA法がないものもあり、この場合はPCR法もしくはウエスタンブロット法でのご案内となります。また、ELISA法において偽陽性(Q9参照)を示すことが想定される場合などは、確認検査から実施していただくことも可能です。
- 拭き取りや洗浄水などを試料として検査できますか?
検査のお受付可能です。
拭き取りでご依頼の際は、お客様側で市販の拭き取りキット(綿棒と希釈液が一体化したもの)をご準備いただき、拭き取ったものを冷蔵便でお送りください。なお、ふき取りキットを選ぶ際は、希釈液にペプトンが使用されているものを避けていただくようお願いいたします。
洗浄水でのご依頼の場合は、検体を採取いただき、密閉したうえで、冷蔵便でお送りください。
拭き取りや洗浄水を試料とする場合、検体必要量は10mL以上となります。
- 定量下限値/検出下限値はどのくらいですか?
それぞれの検査における定量下限、検出下限は下記のとおりとなっております。
※ここに記載のない品目については、お問い合わせください。
- ELISA法(定量下限)
・卵、乳、小麦、そば、落花生(ピーナッツ)、甲殻類(えび、かに)、くるみ、ごま、大豆…総タンパク質濃度として1 μg/g
・アーモンド…総重量濃度として2.5μg/g
・カシューナッツ、ピスタチオ…総重量濃度として1μg/g
・マカダミアナッツ…総重量濃度として2μg/g - ウエスタンブロット法(検出下限)
・卵、乳…およそ10 μg/g
・ゼラチン(豚)…製品等 およそ50μg/g、水(洗浄水、ふき取り検体等)およそ10μg/g - PCR法(検出下限)
・えび、かに、小麦、そば、落花生(ピーナッツ)…およそ10 μg/g
・アーモンド、あわび、いか、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ピスタチオ…およそ数 μg/g〜数十 μg/g程度※1
※1試料の加工度によって大きく変動します。
- ELISA法(定量下限)
- SコースとCコースでは何が違うのですか?
検査日数が異なります。
Sコースはスピードを重視した短納期コース、Cコースは検査日数を長めにいただき、多検体処理することで価格を抑えたコースとなっております。なお、検査の内容に違いはありません。
- 前処理料が発生するのはどのようなケースですか?
下記のような試料をご依頼の場合は、前処理料金3,000円(税別)が必要となります。
- 性質の異なる複数の具材で構成されているもの(例:幕の内弁当など)
- 別添のたれやドレッシング等を混ぜて検査を行う場合。
- 麺、かやく、スープが分かれているインスタントラーメンを全体で(混ぜて)検査する場合。
- その他、通常の前処理とは異なる工程が発生する場合。
- 検査が難しい試料はありますか?
検査方法によって異なりますが、下記のような試料が挙げられます。
ELISA法、ウエスタンブロット法
- 検査の実施自体が困難な可能性がある試料
・増粘多糖類
・その他ゲル状に固まる性質のもの など - 再現性の良い結果が得られない場合がある試料
・脱脂大豆
・シリアルミックス など
PCR法
- 検査の実施自体が困難な可能性がある試料
・増粘多糖類
・その他ゲル状に固まる性質のもの など - 「検知不能」となる可能性が高い試料
・高度に加工されたもの
・加熱・加圧・発酵などを経たもの
・濃縮還元ジュース
・ハチミツ
・油分を多く含むもの
・糖分を多く含むもの
・DNAをほとんど含まないもの
・その他DNA解析を妨害する物質を含むもの(ポリフェノールを多量にふくむ試料等) など
- 検査の実施自体が困難な可能性がある試料
- 特定原材料やそれに準ずるもの以外の食品について、食物アレルギーを引き起こすかどうかを調べることはできますか。
この検査は、それを摂取することで食物アレルギーを発症するか否か、あるいは食物アレルギーの原因があるか否かを確認する検査ではありません。
なお、特定原材料やそれに準ずるものの検査であっても、加工の方法や度合いにより、検出されなかったり(偽陰性)や検知不能となったりすることがあります。このような場合、仮に不検出や検知不能となったとしても、食物アレルギーを発症しないということではありませんので、ご注意ください。
- 化粧品やペットフードなどの食品以外の試料について、食物由来のアレルゲン検査を実施することはできますか。
消費者庁消費者庁次長通知に基づく検査方法は、食品を対象とすることを前提に設計されています。そのため、食品以外の試料では、食品では想定されない原料が含まれることなどから、検査が阻害され、正確な判定が困難となる懸念がございます。
こうした課題に対応するため、弊社では、化粧品を試料とする食物アレルギー(アレルゲン)検査の検証データを蓄積し、検査のご案内が可能な体制を整えております。また、ペットフードに関しても、検査実績がございます。さらに、それ以外の試料につきましても、添加回収試験などを活用することで、より信頼性の高い検査結果が得られる方法のご提案も可能でございます。
検査のご要望がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。
ただし、食品以外の試料では、食物アレルゲンの表示基準等が設けられていないものも多く、結果の評価(本当に安全と言えるのか)が難しいケースもございます。検査をご検討の際は、自社内で基準を設けるなど評価方法を決めておくことをおすすめいたします。
- 1キット使用と2キット使用では何が違うのですか?
1種類のキットで検査をするか、2種類のキットで検査をするかの違いになります。
消費者庁次長通知では「検査特性の異なる2種の検査を組み合わせて実施する(=2キット使用)」となっています。キットメーカーによって検出対象のタンパク質の種類が異なっているために、定量値に差が出ることがしばしば起こるため、当社でも2キット使用を推奨しています。
ただ、社内の定期モニタリングやキットの特性(偽陽性・偽陰性など)を踏まえて、1キット使用で検査されているお客様もいらっしゃいますので、ご依頼の目的に応じて選択いただけるようになっています。
- ELISA法において、偽陽性や偽陰性に関する情報はありますか?
日本製のELISA法キットについては、下記のとおりとなっております。
- FASPEKエライザⅡ(株式会社 森永生科学研究所)
食品反応性データ - FASTKITエライザ Ver.Ⅲ(日本ハム株式会社 中央研究所)
食品反応性データ - FAテスト EIA-甲殻類II(島津ダイアグノスティクス株式会社)
偽陽性偽陰性リスト - 甲殻類キットⅡ(マルハニチロ株式会社)
食品反応性リスト
※精製度により反応性は異なります。
なお、海外製のELISAキットについても、取扱説明書の中で情報提供されているものもあります。
R-biopharm:RIDASCREEN FAST Mandel/Almond(アーモンド)
→偽陽性を示す食品:Apricot stones(杏仁)、Mulberry(桑の実)、Mahaleb cherry stones(マハレブチェリー種子)※カシューナッツやヘーゼルナッツ(生/ロースト)などは、偽陽性対象には含まれておりません。
- FASPEKエライザⅡ(株式会社 森永生科学研究所)
- 品目によって濃度換算が異なるのはなぜですか?
ELISA法検査では、いずれも対象品目に特異的なタンパク質を検出対象としていますが、キットによって換算方法が異なるため、結果の意味合いも下記のとおり異なっています。
- アーモンド、カシューナッツ、魚類、ココナッツ、ピスタチオ、ブラジルナッツ、ヘーゼルナッツ、ペカンナッツ、マカダミアナッツ、マスタード、松の実:総重量濃度(タンパク質以外の、水分、脂質、炭水化物なども含む)
- 上記以外:対象の総タンパク質濃度
なお、検査結果を総重量濃度としてご報告する品目についても、日本食品標準成分表(文部科学省)をもとに、参考値としてタンパク質濃度を算出することが可能です。
例えば、アーモンド(乾)を見てみると、可食部100gあたりのタンパク質量が19.6gのため、総重量濃度が10μg/gの場合、タンパク質濃度は、10μg/g×19.6%=1.96μg/gとなります。
※上記数値は、あくまで参考値としてご利用ください。
- ELISA法で定量範囲を超える場合、どのくらいの濃度かを調べることはできますか?
試料を希釈し、定量範囲内におさまるように調製して検査をすることが可能です。この場合、得られた数値に希釈倍率をかけたものを結果としてご報告します。
ただし、試料の希釈により、実際の含有量とは誤差が生じる可能性があります。検査結果につきましては、参考値としてご確認ください。
- 小麦の食物アレルギー(アレルゲン)検査とグルテンフリー確認検査の違いはなんですか?
食物アレルギー(アレルゲン)検査は測定値を「小麦総タンパク」に、グルテンフリー確認検査では「グルテン」に換算してご報告します。
平成29年03月29日に農林水産省から公表されたノングルテン表示に関するガイドラインでは、米粉・米粉製品等のノングルテン表示にあたっては、消食表第139号消費者庁次長通知別添「アレルゲンを含む食品の検査方法」を準用するとしています。そのため、国内向け米粉およびその製品の検査方法は、小麦の食物アレルギー(アレルゲン)検査となります。
一方、海外基準・認証では、食物アレルギー(アレルゲン)検査とは異なる検査方法が紹介されており、欧米では、グルテンフリーの表示基準をグルテン含有量20ppm未満としています。そのため、海外向け製品のグルテンフリーの表示適正確認に適した検査は、グルテンフリー確認検査となります。
- PCR法の検査結果について、「検出」「不検出」「検知不能」とはどういう意味ですか?
「検出」とは試料に検査対象品目(ex. 小麦、そば…)が含まれること、「不検出」とは試料に検査対象品目が含まれないこと、「検知不能」とはどちらとも判断できないこと、を意味します。実際の検査では以下のように判定します。なお、「検知不能」となった場合、DNA抽出方法を変更することで結果が変わる可能性があります。

- ※洗浄水など、DNAもPCR阻害物質も存在しないと想定される試料の場合、検知不能の結果をもって検出対象品目は含まないと判断する運用ができることもあります。
- PCR法の検査について、どのDNA抽出法を選べば良いですか?
DNA抽出法の選択は、Q&A13に記載の通り、検査結果(検知不能となるかどうか)に影響します。よりDNA精製力の高い抽出法の方が、PCR反応を阻害する物質等の影響を小さくし、検知不能となる確率を低減させます。
参考として以下のチャートを挙げますが、お取引先様などからの指定があればその方法をご選択ください。ただし、食品の形態や成分は多種多様であり、本チャートで推奨する方法でも「検知不能」になる可能性がある一方、推奨方法でなくても「検出」「不検出」の結果が得られることもあります。

※DNA抽出法の解説につきましては、【コラム】PCR法におけるDNA抽出法の重要性と選び方も併せてご覧ください。
- ゼラチン(豚由来)の検査の反応性について教えてください。
ウエスタンブロット法によるゼラチン(豚由来)検査の食品反応性は、下記の通りです。
偽陽性を示す可能性のあるもの
・高濃度の牛、魚ゼラチン(5~10%以上)を含むもの
・豚肉を含むもの
・畜肉、家禽肉、魚肉そのもの(カマボコなど加工品も含む)偽陰性を示す可能性のあるもの
・加水分解コラーゲン